|
||||||||||
| 高松の紙の起源は不明ですが、寛永年間(1624〜1644)に大和国吉野郡の松本長兵衛安清が上山に来て、ウルシ漉しの麻布紙(あざぶがみ)(吉野紙)を伝えたといわれています。しかし、高松にはそれ以前から紙漉きが行われていたという記録があります。 その一つに光明紙がありますが、それにまつわる伝説として、「高松川の両岸に民家があり、この地の住民に紙漉きの技を教えたのは、四国の高松からこの地に移住した僧侶・光明坊である」といわれています。高松の地名も四国の高松にあるようです。 かつては100戸を超える紙漉き農家がありましたが、現在は1戸のみが伝統を守っています。 コウゾやベニバナを栽培し、萱簀(かやす)を編み、紗を簀に張り付けるなど、自給自足の紙づくりをしています。 ベニバナやアイの植物染料で楮紙を染めています。麻布紙は特別求めがある時のみ漉いています。 |
 |
|||||||||
 日本で唯一の石の漉き舟 |
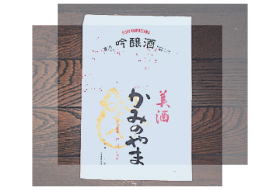 |
|||||||||